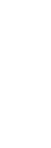Message for Soldier A
- 岡田利規(演劇作家・小説家・チェルフィッチュ主宰)
- 佐野元春(ミュージシャン)
- しりあがり寿(漫画家)
- 岡村靖幸(ミュージシャン)
- 白石(自衛官)
- いとうせいこう(作家・クリエーター)
- 宇川直宏(DOMMUNE主宰)
- 友部正人(シンガーソングライター)
- やけのはら(DJ)
- 髙城 晶平(cero)
- 細馬宏通(滋賀県立大学教授)
- 地引雄一(イーター、テレグラフレコード)
- 藤田貴大(演劇作家)
- 三浦誠音(七尾が南相馬の朝日座で出会ったお客さん、友人)
- 立川吉笑(落語家)
- 難波卓己(Mother Tereco)
- 和田永(Open Reel Ensemble)
- 青葉市子(音楽家)
- マヒトゥ・ザ・ピーポー(音楽家)
- テンテンコ(ミュージシャン、DJ)
- 柿谷浩一(早稲田大学講師・日本文学/文化研究者)
- 蔵屋美香(東京国立近代美術館キュレーター)
- 原一男(映画監督)
- 特殊ワンマン『兵士A』公演時のTwitterまとめ
兵士Aという人物は現時点――というのは2016年6月――においては実在しないがその人物を七尾旅人はまるで恐山のイタコみたいに呼び寄せている。つまりまだ実在していない人物をその実在に先立って呼び寄せている。
このライブ演奏のあいだ彼はときおり咳き込むがそれは兵士Aの派遣された砂漠地帯の砂混じりの風が彼の呼吸器にも入り込んでいるからではないだろうか。
人はこの三時間の映像作品を兵士Aが具体的な顔や名前を持つ実在となる日がそう遠くない将来にやってくるのだと想像することなしに見ることは決してできないだろう。その日が来たらそのときからこの映像の中の七尾旅人は実在人物の表象を担うことになるのだということも。
でもあんなふうに諦めきったような澄んだ目で何度も力強く上方を見据えているということは七尾旅人にはその覚悟だってもうすっかりあるのだ。
だからこの「兵士A」は兵士Aが実在となったあとも七尾旅人の持つ絶望がひときわ明らかになるだけで何一つ色褪せることはないだろう。
七尾旅人の新作「兵士A」に寄せて
旅人は言及する
命に
家族、兄弟に
原子力に
畏怖すべき絶対者に
建築と破壊に
死がプログラムされた兵士に
旅人は言及する
変容の途上にある国に
暴力と死に
光と暗闇に
ポツダム宣言からの未来に
アストロボーイの足音に
沢村栄治の栄光に
そしてショッピングモールに
湿度の高い茂みの映像が
旅人の鼓動と同期するとき
旅人の創造的な魂は
時に南米の湿った森に
時に中近東の砂漠に
飛翔し、墜落し、
分解し、再生する
ジャズ、フォーク、オペラ、スポークンワーズ、エレクトロ、ダブ、アバンガルド、童謡、神話からサイエンスフィクションまで、
語られる言葉と歌われる言葉の狭間に
旅人の唸りのループが滑りこむとき、
私たちの現実は、一瞬、更新する
雨や風を想わせる旅人の爪弾くギター
自由に動き回るアルペジオが
朝に夕に、春に秋に、
唯物から唯心に
過去から未来に、
美しい警告を残して消えていく
旅人の2016年作品「兵士A」は、ミンガスと邂逅したジョニミッチェル、フィリップグラスと邂逅したパティスミスらの仕事と同質の価値を持つ。
世界という名の劇場、その舞台がどんなに混濁しても旅人の目的は高潔だ。
僭越ではあるが、僕はそう信じる。
僕たちはかつてやさしくなろうとしていたんじゃないだろうか。
季節や自然や人の、僅かな兆しから豊かな感情をくみ出し、薄く広がる曖昧なものや、小さく弱くとりとめもないもの全てをないがしろにすることなく、変化と調和を繰りかえし、喜びに奢ることなく、哀しみに溺れることなく、振り子の中心に常に微笑みがあるような、そんなやさしい世界を目指していたんじゃないだろうか。
だけどいつのまにかやさしさより強さが求められるようになった。
ナイーブであることは弱いことであり、タフさこそが必要とされるようになった。
それもまたひとつの真実であるにしても、そうやすやすと目指していたものを捨て、
力と怒声と分断の社会へと舵をきっていいのだろうか。
七尾さんの歌を聴いていてそんなことを思った。
この作品にわかりやすいメッセージなどない。
ただ「今」に対する静かで深い視線があるだけだ。
七尾さんの歌はやさしくて、そして強い。
この歌が終わってしまったやさしい時代へのレクイエムにならないよう、
とりあえずは、この歌が雨となって世界中に降り注ぎ、
すべての弾の込められた銃を錆びつかせてやればいいのに。
電気などなく明かりがない時代
録音など出来ない時代
夜は本当の暗闇だった頃
本当の夜の姿と本性を剥き出しにしていたんでしょう。
その頃
みんなどれだけ神経を研ぎ澄ませて、音、その場の空気を
感じてただろう?
色んな時代を行き交いながら
呆然と映像をみてると
音と映像と静寂、咳、ノイズ、
エラーのような軋む音
全てが物語になって作品になって
この作品には特別なものを
特別な体験をしてることを
知らされる。
この時代にこのような作品を
作ることにみんなはどんな
意味を感じるだろう。
僕はとても大事な体験を
した気がしました。
集団的自衛権の行使を巡って世間の怒りの矛先は政府に向いていた。
自衛官を守れと周囲では運動が起こり拡声器で叫ぶ人びと。
だけど国会前が怒りの渦にのみ込まれた状況を見るとそれすら戦争の様に思えて心が引き離される様な感覚だった。
そんな中、聴こえてきたのが
「兵士Aくんの歌」
歌の中のAくんは弟であり彼氏であり我が子であり、つまり自分にとって欠けがえのない大切な存在。
自分にも必ずいる大切な存在と重ねた時に永遠の別れを感じざるを得ず胸が締め付けられる。
何に反対を表明する訳でもなく「その時」がきた時に人間ならどう感じるかをそっと問い掛ける様な優しくて素朴な歌。
優しくて素朴な歌であればこそ家族の様な距離感を感じて涙を止められなかった。
東日本大震災で福島にて人命捜索をしている時、原発は世間から悪の権化に祭り上げられ自分自身もその感情に引っ張られながら丘に登り、初めてその哀れで悲しいまるで生き物の様な姿を目にした時、新たな感情に突き上げられ泣いた。
その時の感情を旅人さんの歌に重ねる自分がいる。
暴走して加速する列車からは何も見えないけど旅人さんはそこから降り立ち、霞む景色の向こうにある真実に目を向け、栄光の影に隠れてただひたすらに国の為にと信じて命を捧げてきた限りなく純粋な人達の小さくて大きな名もない物語を拾い上げて歌にしている様に思う。
僕はAくんになる可能性がある。
戦争を僕らは体験していないけど兵士Aくんを想像して涙を流せる人であり続けたい。
そして時代と人の間に立って常に中立で優しい歌を歌い続ける旅人さんの命を燃やしたこの作品が多くの人の行き先を照らす光になる事を願っています。
思えば『911FANTASIA』で凄い奴が出たなと驚いたのだった。
あの時も奴は「芝居」を取り込んでいた。
演劇と音楽の境界が本来なく、
それがましてや社会と離れているはずがないことを人類史的に「感じる」。
まず何より憑依ありき。
別次元から降りてきた他者の言葉は預言。
予言とは異なる。
ここには預言が響いていて厳粛なほどだ。
抉りとった「心」の・ようなもの
七尾旅人.....僕はもうかれこれ15年間程前から、この現代日本に於ける稀少な吟遊詩人の表現を追っている。だから、だからこそ「兵士A」を見逃したことだけが、去年の僕の心残りであった。そこで、未だ観ぬものの特権として、TWITTERでライヴ帰りのフォロワー達の驚嘆のつぶやきを漁ったり、『911FANTASIA』との連なりを探ったり、また「この国の どこかで まだ 君が生きている」...この詞からルバング島より帰還した"最後の日本兵"小野田寛郎氏を重ねたりして、ひとり「兵士A」の妄想に浸っていた。その上で、美化される出来事の地獄の真実と、極限状況の阿鼻叫喚を、七尾旅人は描いているに違いない!そう確信していた!!!!!!!
あれから、8ケ月…。遂に「兵士A」は忘れ形見のように、ブルーレイディスクに姿を変えて僕の目前に立ち現れた!!!!!!! そして、僕の想像の遥か数十億光年の彼方に、この作品が君臨していたことに恐れ戦くのであった.....。
1人目の戦死陸上自衛官=「兵士A」の、およそ100年間に及ぶ壮大なサーガは、嘗て自らが体感した全ての表現に似ておらず、しかし、体感した表現のあらゆる要素が入り乱れていた。つまり、これは勿論、音楽であり、そして、演劇であり、漫画であり、映画であり、そしてまたパフォーミングアーツでもあって、更には、個が放つ大衆芸能の総体であるかのように雄弁だった。落語、講談、浪曲、義太夫.....全ての要素がここにあるではないか? しかし、この作品は、そんなカテゴライズ自体を拒絶しているかのように、最終的には、そのどれにも回収されておらず.....にも関わらず、それら全ての表現の底流に脈打つ、創作の正体が剥き出しになっているかのように無防備だった。七尾旅人の全身全霊から放たれる、創造の根源としての身体的衝動と、また個体と外界(社会)との相互作用、そしてなにより七尾本人の現世を生きた痕跡が、物語の主人公である「兵士A」のメディウムと化して滲み弾ける。Aは、Bであり、Cでもあり、またXでも、Zでもあって、あなた自身、そして僕自身でもあるのだ。
しかし特筆すべきは、この"特殊ワンマン"で構成された、"うた達"は、フォーク文脈のクリシェとしてのプロテストソングなどでは毛頭ないということだ。つまり、この表現は、社会運動や反戦運動と結びついた直接的な政治的抗議ではないのだ。疑いもなく妄信してきた政府が、戦争国家へ向け強権的に動きだし、そして、世界が少しずつ破綻して行く不安と、焦燥と、恐怖を、物語の登場人物になりきり、渾身の力で描き出しているのだ!!!!!!!
この映像作品の中には、それら七尾の繊細な心の揺らぎを中心に、観念的な口寄せによって降霊した様々な登場人物が顔を出したり、またその惨状を目撃した観客の情動が乱反射したり....自己と他者と架空の人物が、分裂的に歪んで溶解し合って空間に渦巻いた、生命力の束として真空保存されていた!!!!!!! このディスクには、音楽も言語をも超越した、ありとあらゆる人間の感情が詰まっているのだ!!!!!!!
そしてその演奏空間を再生することによって、収録された生命力は空気感染を果たし、我々視聴者の精神に多層的に作用する!!!!!!! そう、この作品は抉りとった「心」の・ようなものだ!!!!!!! その証拠に観賞後、取り出した銀盤が、人間の心臓に見えてきたではないか? だけど、誰も知らない、ほんとは知らない....。しかし遂に、この映像を目撃してしまった僕は、「兵士A」は小野田寛郎氏のように生き残ってはいなかった、という物語を知ることとなる。「兵士A」は、人を殺し、そして人に殺されていたのだ....。
「私は戦場での三十年、 生きる意味を真剣に考えた。戦前、人々は「命を惜しむな」と教えられ、死を覚悟して生きてきた。戦後、日本人は何かを「命がけ」でやる事を否定してしまった。覚悟をしないで生きられる時代は、いい時代である。だが、死を意識しない事で日本人は生きる事を疎かにしてしまってはいないだろうか?」最後の日本兵、小野田寛郎氏は、戦後を生きる我々にこのような言葉を残し、警笛を鳴らした。そして、いま、我々は、世紀を超えて、文字通り「命がけ」の創造に向かい合うこととなった。一心不乱な七尾旅人の覚悟に触れて「命」の意味を上書きしてしまったのだ!!!!!!! だからこそ声高に叫びたい!!!!!!! これは、壮絶な「玉砕」などではない。極限の「創造」なのだ、と!!!!!!!
僕は、七尾旅人と同じ時代を生きていることを誇りに思う......。
七尾旅人の「兵士A」
七尾旅人の「兵士A」を見ました。戦争に引きずりこまれそうな内容でしたが、ここは踏みとどまらなくては、と思いました。その夜ぼくはこんな夢を見ました。
かがみこんで顔にスミを塗っても、カラシニコフを手に立ちあがっても、ぼくたちは歌を離れない。歌を離れなければ戦争は来ない。風呂屋に行っても、居酒屋にいても、ぼくたちは歌を離れない。歌を離れなければ戦争は来ない。兵士Aに扮しても、舞台で水を飲んでも、七尾旅人は歌を離れない。歌を離れなければ戦争は来ない。歌を離れない暮らしがあれば、ぼくたちの暮らしに戦争は来ない。これは戦争を表現した歌だけど、ぼくたちは戦争をしたいのではなく、歌いたいのだ。歌から離れようとは思わない。旅をしていても、人として生きていても、ぼくたちは歌を離れない。七尾旅人は歌を離れない。
こんなことを思いながら、ぼくは再び深い眠りに落ちたのでした。
七尾旅人、ベストライブ! と、いうと、七尾旅人のポップ・ソング作家としての側面を支持する向きや「ミスの多いライブだった」と記述する本人、などから非難されてしまうかもしれない。
しかし、七尾旅人にしか出来ない切り口での表現だということ、また、クロニクル性を持った、物語を内包する語り口は、(リリース時には「誰も分かってくれなかった」と、本人が後述する)2007年リリースの「911FANTASIA」においても用いられていた技法であるということ、ビートボクサー、聖歌隊、動物や昆虫を含むヴォーカリストのみのプロジェクト「VOICE!VOICE!VOICE!VOICE!VOICE!VOICE!VOICE!」などでも試行されていた、演劇的な総合表現、全体を貫くコンセプト、が、ある、という意味でも、そして、その様々な要素が、(まさに百人組手的に)実験と実践の上に、とぎすまされ、一朝一夕どころか、千朝千夕でも常人にはたどり着けない、表現としての独自さ、強度、をもって、圧倒的な説得力で、立ち現れたという面で、「ベストライブだった」、と、言って過言ではないだろう。
それは、創造力の限界値を探索し、人類の叡智を駆使して音楽表現の可能性を拡張するような試みで、狭義の使い捨てられていく大衆音楽の幅を(表面上は)何処までも逸脱しながらも、同時に、根源的で普遍的な表現に到達するという、ウルトラCである。
深い闇の奥、薄っすらと像を見せる、誰も目を向けないような小さなその姿、息吹、声にならない声。心の奥にいる兵士A。その所作に、しっかりと目を凝らす。それをなかったことにしたり、ステレオタイプに描いたりは、けっしてしない。その固有の、喜びの、悲しみの形を、生を、丹念に丹念に掬い取る。それは、どこまでも果てしなく、もう帰って来れないのではないかというほど深い闇の奥へ、命綱もなしに、踏み込むような作業だ。
そのモチベーションの根源は、奇を衒った意味のない突飛さや、ディストピアに浸る耽美な快楽性などではなく、生命の、そして音楽を含む、その固有の生命が作り出す事象への(逆説的に、もしくは最終的には)信頼、で、あろうか。
そう、これは、大きな音楽だ。もしかしたら、掃いて捨てられるかもしれないような小さな塵が集まって出来た大きな音楽。相当大きいのではないでしょうか。
富山で観た旅人さんのライヴが強烈に印象に残っている。通常のライヴセットのなかに織り込まれた“兵士Aくんの歌”と“Almost Blue”、更に言えばその流れで演奏された“サーカスナイト”も含めて忘れられない。『兵士A』の世界を経て聴いた“サーカスナイト”はそれまでとは違い、まるで懐かしい時代の歌のように遠くに感じられた。それは二度と帰ることのできない場所にある美しい音楽だった。
これからぼくは、旅人さんの楽曲の全てを『兵士A』以降のものとして聴くのかもしれない。より危うく、より貴いものとして。
一人の兵士の姿をした七尾旅人が、ある年代記を唱えるうちに危うい旅に転がり出る。正義を為す旅ではない、敵に味方に憑依し、誰もが今にたどりついた理由を持っていることを一人の体で明らかにする旅、一時間、二時間、旅はどこまで続くのか、それでもなお兵士は顔をあちこち黒く塗り、我知らず銃を担い、鉄を激しく叩く。ことばはすばやく繰り返され、声は咳き込み、腕は弦の上で小刻みに音にならない音をたて、もはや音楽までもが痙攣し危機にさらされている、まさにその危うさのさなかで兵士は、小さくかすれたうたを口ずさむ。うたの禍々しさのまっただ中でうたを携え続ける七尾旅人の、目をそらす間もない、圧倒的な三時間。
それは事件とも言うべき、あまりにも鮮烈なライブだった。
兵士Aとなった七尾旅人が、その全存在を賭けるかのように、音楽で今の時代と真っ正面から対峙した壮絶な3時間。戦争、原発、そして死という重すぎるテーマに貫かれたステージでありながら最後まで惹き付けられるのは、彼の歌に命の輝きを感じるからだろう。
七尾旅人を知ることによって初めて歌というものに強い関心を抱いた僕は、歌は命そのものではないかと思うようになった。彼の歌に内在する命の輝きが、重い現実の中に生命の温もりに満ちた希望を生み出すのだ。
この日、超満員の観客が皆、張り詰めた空気の中でじっと聞き入っていたのが印象に残る。ツイッター上の感想も、ほとんどがこの日のライブの意味を真剣に受け止めようとするものばかりだった。若い観客達にとっても『兵士A』がリアリティを持って感じられる時代になったのだろう。
この日のライブが映像作品化される意義は大きい。たくさんの兵士Aたちが死の宿命に抗い、その命の輝きと希望を一人でも多くの人に伝えていって欲しいと切に思う。
旅人さんの、あの眼に映る光景は、でもやっぱり現在なのだ。真っ最中の音を鳴らす彼の「あの日」の姿を、眼裏に焼きつけて、ぼくらもまた生きていくのだろう、こんな時代を。
たとえば、自転車の音を
(下記、2015年11月19日『七尾旅人 特殊ワンマン「兵士A」』の翌々日、2015年11月21日に Twitterへと投稿。2016年6月14日改稿。筆者記)
坊主頭の少年が、ラジオのつまみを懸命に調節している。きれぎれに聴こえてくる、ナット・キング・コールが彼のお気に入りだ。だがその美しい歌声は、激しいノイズと、そしてアナウンスで中断される。「臨時ニュースを申し上げます」。空襲警報。
Aくん。裕福とは言えない家庭に育った彼は、父親に買ってもらった自転車に乗るのが好きな少年だった。長じて彼は兵士となり、敵を(少年兵を、恋人達を、難民を、故郷喪失者を、傭兵を、自分とそっくりな者を)殺すだろう。そして、自らも殺されてゆくだろう。
2015年11月19日、七尾旅人公演『特殊ワンマン「兵士A」』を観た。
七尾旅人は、語り部としての資質を強く有する音楽家だ。病者と娼婦の恋を語り、心優しき殺人者のことを語り、小さな地方都市の一家族について語る。今回、彼が語ろうとするのは、「兵士Aくん」の物語。そしてその周囲に現れては消える、過去/現在/未来のひとびとの物語だ。
七尾旅人の天賦の才のひとつが、ひとを惹きつけるその美声であることは疑いを容れないだろう。だがその声は、しばしばこの上なくグロテスクな風景に踏み込む。ここでいうグロテスクとは、生命そのものがぎりぎりいっぱいに満ちて外界へと溢れ始める、そうした境のことだ。そしてそれは、彼の声によって、音楽の美しさへと変換されてゆく。
今回の公演から言うなら、たとえば、戦死者に向けた「あなたのなきがらに、えい、こー」という異様な旋律であり、少年兵の物語において囁かれる「蜂の子が落ちてくる」という幻視であり、機械音の打撃の上で叫ばれる “I'm warbot” という惨たらしさに満ちた宣言だ。崩壊感そのもののようなその音楽に、聴き手が善悪の判断を越えて、よろこびを感じなかったと言えるだろうか。
七尾旅人は、己の裡に潜む戦争を知っている。自由を愛し、盲従を望み、小さな幸福を希い、破局を欲し、愛を求め、殺戮に身を投じる。そのような矛盾に引き裂かれた「ヒト」という生命から、彼は目をそらすことができないのだ。
さきほど、七尾旅人の「語り部」としての資質について触れた。だがそれは、兵ならざる者が兵のうたを歌い、難民ならざる者が難民のうたを歌い、死者ならざる者が死者のうたを歌う、そうした不遜さをどこまでも避けがたく伴う行為だ。
にもかかわらず、彼にとって、これらの物語は歌われなければならなかった。それは、殆ど信仰に似たレベルの物言いになるのだが、他のいかなる芸術や学術や記録によっても零れ落ちてしまうなにものかを、うたならば抽出し保存し、永遠に遺すことが可能だからではないのか。
ひそひそひそひそ、だからつまり - 。ひそやかに歌われてゆく。なかったことにされた、なかったことにされてゆく、なかったことにされるだろう、なにものかの物語が。たとえば、Aくんの自転車の音が。このとき、Aくんは架空からそっと歩み出す。
七尾旅人の希いは、裁くことでも糾すことでも教え諭すことでもない。
おそらく、彼の希いはただ、歌うことだ。忘却の定めにある有限の生命を、うたに変換しようとする、怖ろしい、しかし祈りに似た希いだ。
公演終盤、『再会』の章において、梅津和時が登場する。国防軍服姿の七尾と、旧日本軍の軍服を纏った梅津。時を隔てた、ふたりの死者について語るかのように。
あなたにはなにも言わずにいよう/この命で完全に守り抜く/ひとかけらの危うさも/けして残さぬように(『完全なる庇護』)
かなしい世界は終わらないのと言う/もしも願っても変わらないよと言う/だけど誰も知らない/ほんとうは知らない(『誰も知らない』)
警報と爆撃の轟音に満ちた公演の最後、まるで讃美歌のような二曲。『完全なる庇護』の祈りは、何度も空襲音に掻き消される。そのあとの静けさの中で歌われた『誰も知らない』。曲が終わるとき、Aくんは、兵士になる前、少年のころ愛した自転車のベルをもう一度鳴らした。
終演。ぼろぼろに消耗した七尾旅人の肩を、梅津和時が抱く。その笑顔は、苦難の旅を経て家に帰り着いた少年を戸口に出迎える、父親のようだった。
(了)
京都から東京へ。
僕は2010年10月、師匠・立川談笑に弟子入り志願した。
その半年前、2010年4月。吉祥寺。
弁天湯での風呂ロックで初めて旅人さんのライブを観た。
呆然とした。
2007年。
「911FANTASIA」で、こんな表現が可能なのかと衝撃を受けた。
23歳だった当時の僕は、目指すジャンルすら違うのに、
こんな作品を産み出せる人が存在する世界で、
自分は何か表現することができるのだろうか。
怖くなった。
それでも3年という年月で自信を取り戻し、
というか受けた衝撃を忘れてしまった僕は、
落語をやりたいと強く思うようになっていた。
「911FANTASIA」で一度圧倒的な衝撃を受けた僕は、
七尾旅人の免疫がついているつもりだったのに、
生で観た旅人さんのライブは桁違いだった。
旅人さんがワンフレーズ口ずさむだけで、
ぐわぁーっと場が支配されていく感じ。空間制圧力。
しかも、舞台上には旅人さんひとりだけ。
それは、使っている道具が違うだけで、
僕には落語と同じように思えた。
同時代に七尾旅人という凄まじい表現者がいる中で、
自分にしかできない表現ってどんなものだろう?
入門して6年経った今でも答えは見つかっていない。
そして今回の「兵士A」。
この6年間で旅人さんは何回死んで、そして何回生まれ変わられたのだろう。
何生分かの時間を経てないと辻褄が合わないような
その進化、その深化ぶりに、また衝撃を受けて、
そして怖くなった。
旅人さんが紡ぐ音たちが頭の中に様々な情景を投影する。
そこには優しさ、強さ、悲しみ、恐怖、美しさ、希望、全てが生きている。
旅人さんの、人々の、そして兵士Aくんの。
昨年11月に行われた特殊ワンマンで観たその光景は、
映像になっても、いや、むしろ映像になったことでより一層強く感じられた。
今を生きる私達の感覚から離れていく過去の想いは、
「兵士A」を目撃した人たちの心の奥底から蘇ってくることだろう。
この作品が放つ美しいひかりが、その道しるべとなって。
「兵士A」を観ていたら、子どもの頃に空想したことが蘇ってきました。空を飛びたいと神様に願った山羊が、空を飛ぶ力を手に入れて世界を旅するのだけれど、そこに広がる数々の惨禍に絶望して体中の毛穴から涙を流して溶けてしまう、という空山羊の物語。きっとテレビから流れる戦争の映像が影響したんだと思います。その頃、21世紀を前にして、明るい未来像も囁かれていたけれど、なんだか怪しいということも感じていました。
あの震災で再び目の前にはっきりと科学による廃墟が現れて、そして再び東京にカンフル剤を打つようにオリンピックがやって来ようとしている。そしてこのまま判断を誤れば再び戦前を迎えてしまうだろう。この作品は遠くない将来を目を細めながら必死に見通して歌っている、と同時にそんな今を未来から振り返って歌おうとしている。そんな時、今はまだ顔を持たない「兵士A」と、何十年後から振り返っても忘却された記号となってしまう「兵士A」、そしてかつての「兵士A」を知らないこと、日々戦地で生まれる「兵士A」の個について想像しないこと、全てがダブって感じられます。そこに血流を伴った1人の存在を憑依させて死と生を帯びて紡がれていく音楽と歌に、胸が張り裂けそうになりました。そこに内包された時間軸と七尾さんの根源的な魂から湧き起こる生命力に圧倒されました。衝撃と余韻にくらくらし続けています。
各地でエネルギーを供給する巨大な銀の輪がぐるぐると回り、世界経済がぐるぐると回り、政治が刻一刻と変化していく渦の中で、簡単に割れてしまう弱い存在に寄り添おうとする。愚かしいことも美しいことも何度も繰り返してきているからこそ、繰り返し問い続けようとする。「もしも願っても 変わらないよという」でもなんとか本当のひかりを探して表現していくのだと思います。この作品からその大切さと勇気をもらいました。今出会えたこと、産み出してくれたことに感謝です。本当にありがとうございます。
願っている。
兵士A君が持った銃は、
音楽になった。
音楽がもつ魔法を
わたしたちは知っている。
あのころ
もしくはこれから
鳴っていた、鳴るであろう
音楽のひびきが、
兵士A君となった旅人さんか
出ていって
受け取ったわたしたちに、
もう、
銃は 戦争は なくていい。
あんなにきれいな眼が
戦場にも すぐ傍にも 自分にもあるのだから。
2010年8月15日、大阪の劇場でキャタピラーの公開後、若松孝二監督に感想を伝えた。「理解できなかった。でも理解しきれないことの幸せはわかった」と。
氏は憤慨し、スタッフがそれをなだめた。凍りついた劇場、若松孝二のサングラスの奥の目に怒りの色がさしていた。ぼくはあの色をきっと忘れないだろう。
わたしは戦争モノが嫌いだ。どこまでいっても戦場に立つ者の気持ちも、みおくる者の気持ちを理解できないのだ。
この日の七尾旅人をイタコのようだと評する人間もいるだろう。それはちがう。この日の七尾は嘘を歌っている。そう、その声には願いがある。それはこの作品が現在という地点から歌うたいによってつむがれた表現であった証拠だ。未来にはじまるであろうドキュメンタリーでも予言でもなく事実でもない。そこがひたらすに美しく、美しさの分だけ真実だったのだ。
「この光を美しいものにかえなくては
ぼくらの光にかえなくては 」
表現とはなんだろう。
軍服とクラシックギターはどうしてこんなに不釣り合いなのだろう。わたしはやはり兵士Aの気持ちがわからない。それは旅人も同じであっただろう。うたの中で知っていったのだ。自らが集めた億千の言葉の意味を、メロディの連なりと兵士Aの見ていた光の中を旅しながら旅人確認していた。少なくともわたしにはそう見えた。
ぼくはいつか、いつの日か、くだらない話しをしながら、ただ新しいうたを歌ったり聞いたり、うたがそれだけでよかった日のように、表現者としては退化したと後ろ指をさされ、嘲笑される声も聞こえないくらい大きな声で笑って、何もないけど幸せだなって思える沈黙の次に美しい日々の中で七尾旅人とあいたい。
その日まできっと彼は戦うのだろう。何と?誰と?答えはあるのか?正しさって?わからない。わからないけどそれだけはなぜかわかるんだ。
ぼくも戦うよ 。
おやすみなさい。
昨年の11月19日、私は渋谷WWWにいました。七尾旅人さん特殊ワンマン「兵士A」を観る為です。会場は超満員で一番後ろのブロックで時折つま先立ちをしながら見た景色を今でもめちゃめちゃ覚えています。かなり特殊な環境でした...ひらのりょうさんの映像と梅津数時さんのサックスと共にステージ上で確かに闘っている兵士Aくん、こと旅人さんがいました。それは普段のWWWの光景とはまるで違いました。お客さん達はただ見守ることしか出来ず、ひたすらそれぞれ何かを感じ考えていたのだと思います。堪えきれずに涙を流している方もいました。
あれから半年以上経ち、あの公演が映像作品として形になると知った時、とてもザワザワとしました。忘れてはいけない!声が聞こえた気がしました。ハッとしました。私たちは常に戦前を生きているのです。目を逸らしてはいけない!そうやって兵士Aくんはずっとずっと称え続けます。兵士Aくんの声、気付かせてくれてありがとう。もう絶対忘れないよ。
畏友・七尾旅人の新作によせて
戦後生まれの七尾旅人に、直接的な戦争体験はない。あるのは「戦後」の経験だけだ。
だがそれをそのまま原体験にし、戦後という時代の先端の位置から歌うことを、彼は選ばない。自明視された「戦後」(の捉え方)を、いま一度大胆にひっくり返し、自分の拠って立つ場所を更新し、言葉を紡いでゆく。「戦後」を「戦前」に変えることによって――。
そもそも文学的に言えば、全ての芸術作品は、既に起こったある戦争に対する「戦後文学(的)」と考えられる。同時に、あらゆる芸術的表現は、これから起こり得るかもしれない一つの未知の戦争をめぐる「戦前文学(的)」であるとも言える。おそらく多くの人々が忘れているであろう、この《戦後は戦前でもある》という逆説的な世界認識と感性から生み出された傑作こそ、最新作『兵士A』に他ならない。
「今、戦前を、戦前を生きています。」(「戦前世代」)に始まり、「だけど誰も知らないほんとは知らない」(「誰も知らない」)という歌詞で終わるこの作品は、よく知り得ているはずの《戦後》を、まだ見ぬ《戦前》へと反転させてみせる、歴史とその認識をめぐるアクロバチックな挑戦=創造と言えよう。
作中には、さまざまな戦後史の断片が登場してくるが、そのどれもが、私たちの知っているもの・ことに見えつつも、他方で、どこか微妙に違った影を刻んでゆく。作品が進むにつれて、それら歴史の欠片は、徐々に異形なものに変貌しながら感受されてくるのだ。それは「戦後」が姿を変え、逆襲してくるかのような現象である。“未来の戦死者”兵士Aのまなざしを借りて、既知としてきた《戦後(史)》が、《戦前(史)》として異なるかたち・意味・重みを持ち始める時、私たちの内にある歴史観と、そこに支えられた頑丈なはずの「今」は、音を立ててぐらぐらと揺らぎ始める。
作品を観ている間、多くの人は、如何ともしがたい不安や戸惑いを幾度となく感じることだろう。それは「戦後」を凝視してきたはずの自己を、作品の《戦後―戦前》を切り結ぶ想像力が容赦なく突き刺し、批評してくる瞬間である。その痛みに耐えながら、一人一人が考え、応答しなければならない。
――「今」は戦後か、それとも戦前か。そもそも「戦後」とは何のことか。一体、自分はいつを生きているのか。
作品を通じて、兵士A=七尾旅人が突きつけてくるこの問いは、現代を生きるすべての人間にとって、普遍的かつ根源的なものである。七尾旅人の全身全霊をかけたそれが、「今」と「戦後」に新たな楔を打ち込み始めた。この稀有で凄まじい実践を、見逃してはならない。
わたしは美術館のキュレーターです。
絵画や彫刻といった美術作品を展示し、この100年ほどの美術と社会の動きを見せるのが主なしごとです。
関東大震災(1923年)、治安維持法公布(1925年)、幻の東京オリンピック(1940年開催予定)と日中戦争勃発(1937年)によるオリンピック開催返上。3.11以後を思わせるこんな流れを、わたしは現在のたとえ話として観客に示します。過去は現在と未来のひな型なのです。だから、沢村栄治からウォーボットまで、長い時間の中から似た出来事を探し出し、結び合わせる七尾旅人さんのしごとにとても共感します。
もう一点。「兵士A」に含まれる歌はどれも主語があいまいです。父ちゃんが原発で働く「ぼく」はA君とどんな関係なのか。ショッピングモールで別れを惜しむのは誰なのか。「あれはわたしの彼、あれはわたしの子」と、ひとつの歌の中でもA君に対する発話者が入れ替わります。そこでわたしたちは誰がいつの時代に何を語っているのかを考え、自分なりのストーリーを編み出さねばなりません。
こんなばらばらの状態をひとつに支えるのが、七尾さんの身体と声です。だから七尾さんの身体と声は、聞く人それぞれが考えたストーリーを持ちよる場、フォーラム(集会所)のように機能します。そして、このフォーラムとしての身体と声は、生々しく機器のトラブルにいらついたり咳込んだりすることで、「兵士A」の世界を、舞台の上の絵空事ではなく、わたしたちの現実にしっかりと結び付いたものにするのです。
敗戦の年に発布された平和憲法の下で生まれた自衛隊。そして最初の戦死自衛官Aを出してしまったニッポン国ーーこの“戦後初めて戦死した自衛官A”というイマジネーションに、私は虚を突かれてしまった。打ちのめされて考え込んだ。いや、これまで意識の中にはあったかも知れない。が口に出すのが憚れるからか、臭い物には蓋、の例えどおりなのか、無理矢理押し殺してきたように思う。それを七尾は白日に下に晒してしまったのだ。
もう誰も逃げられない! “戦後、戦死した自衛官B”というイマジネーションを私自身が持てるかどうか?
と問われている。そして誰かが“戦後、戦死した自衛官C”というイマジネーションを……。
想像力が枯渇、衰弱死したも同然のニッポン人たちが、七尾旅人の提起したイメージをよく理解できるだろうか?
という不安がよぎる。が今は、かくいう私自身が、七尾旅人に続くことができるのか? と胸に問おう!